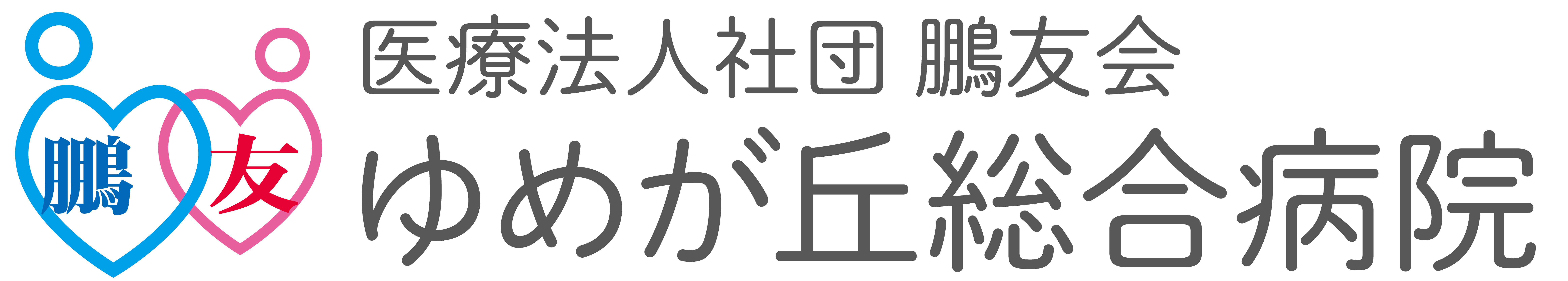感染対策室
感染対策室の紹介
安全かつ良質で高度な先進医療を提供するため、院内で発症する感染症を未然に防ぎ、院内の外来・入院患者と職員の安全と健康を守り医療の質の保証に貢献することを業務方針にしています。そのため室員は細菌学、感染症学や感染制御学に精通した医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務員で構成され、多職種による感染対策チーム(ICT)として組織横断的活動を特徴としています。
感染管理に関する基本的な考え方
ゆめが丘総合病院(以下当院)における院内感染対策の基本指針に則り、以下の基本方針の沿って感染管理に取り組んでおります。
組織体制
感染対策管理室は病院長直轄のスタッフ機能として、組織横断的に活動できる組織配置としています。
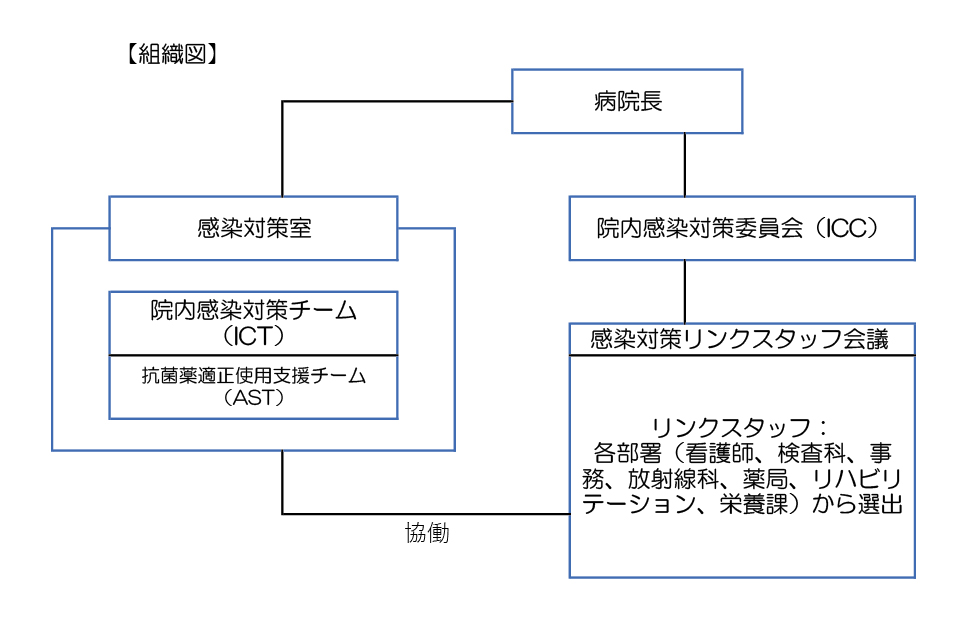
感染対策のための委員会
【1】院内感染対策委員会(ICC)
病院長をはじめ、組織横断的な構成員からなり、ICTで検討した感染対策に関する問題・改善策の審議、院内感染管理の方針と関連する提議事項の決定機関(諮問機関)とし運用しています。
ICCでの審議事項
(1) 院内感染対策に関し、施設、設備、それに伴う予算など事項
(2) 院内感染対策に対するマニュアルの作成に関する事項
(3) 院内感染対策についての周知徹底や啓発に関する事項
(4) 院内感染が判明した場合の報告とその対応に関する事項
(5) その他、院内感染に関すること
委員会は職種横断的に、診療部、看護部門、薬局、臨床検査部、事務部門、その他必要な部門を代表する委員によって構成しています。
【2】院内感染対策チーム(ICT)
感染対策室を中心に、具体的な院内感染対策を実行していく実働部隊として、迅速かつ的確な感染対策方法や情報の伝達を行うことで感染防止対策を推進しています。
(1) 院内での感染症発生の速やかな把握と対策を講じる
(2) 感染防止対策に対するコンサルトに応じ指導・評価
(3) 院内感染対策マニュアル及び各種マニュアルの作成と改訂
(4) 職員への感染対策に対する教育
(5) サーベイランスの実施とフィードバック
(6) 定期的なラウンド週1回
(7) 職業感染管理
(8) アウトブレイク発生時の対応と再発防止への取り組み
(9) その他 院内外における感染対策に関する事項
*地域連携加算に係る活動(相互評価・合同カンファレンスなど)
ICTの構成
① 院内感染管理者(医師) 2名
② 感染管理認定看護師 1名
③ 薬剤師 1名
④ 臨床検査技師 1名
⑤ 看護師 1名
⑥ 事務 1名
【3】抗菌薬適正使用支援チーム(AST)
薬剤適正アクションプラン(AMR)に基づいて、抗菌薬適正使用支援(AS)を実践し、抗微生物薬適正使用を図る。その役割として、感染症治療の早期モニタリングとフィードバック、微生物検査・臨床検査の利用の適正化、抗菌薬適正使用に係る評価、教育、啓発を行うことによる抗微生物薬の適正な使用の推進を図る。
主に以下の活動を行う
(1) 感染症治療の早期モニタリング及び主治医へのフィードバック
(2) 微生物検査・臨床検査の利用に関すること
(3) 抗菌薬適正使用に係る評価
(4) 定期的なAST介入状況とサーベイランスの報告
(5) 抗菌薬適正使用推進のための教育・啓発
(6) 抗菌薬使用指針の作成及び改訂
(7) 定期的な採用抗菌薬の見直し
(8) 他施設との抗菌薬適正使用の情報共有と連携、コンサルテーション
【4】感染管理に関する教育・研修

職員の感染に対する意識向上を図るために、感染対策の基本的な考え及び具体的方法などについての教育・研修を行う。また外部委託業者についても必要に応じて研修などを行う。
【5】院内感染対策マニュアルの作成・改訂
各ガイドラインを参照し、現場に則したマニュアルの作成・改正を行い、マニュアルの整備をし、医療関連感染症の発生予防に努めています。
【6】地域連携・院外活動
(1) 感染対策向上加算1施設同士での相互評価を行っています。
(2) 感染対策に関するカンファレンスを感染対策向上加算2および3施設と実施し、情報交換など行っています。
(3) 横浜市感染防止対策支援連絡会(YKB)に参加し、横浜市内の医療機関との院内感染対策を支援する活動を、ネットワーク参加施設と共に行っています。
【7】感染及び届け出を要する感染症に係る報告
「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律」に規定される診断および届け出の手続きを適切に行います。
【8】その他
サーベイランスの実施
*厚生労働省サーベイランス事業参加
【検査部門】
細菌検査の結果から、分離頻度や抗菌薬感受性に関するデータを収集し、薬剤耐性菌の分離状況を把握しています。